※この記事は2020年3月に書いた「子どもたちと踏み込み温床を作ってみたけど、踏み込み温床ってなんだろう?」を加筆修正の上、2025年3月に再公開したものです。
みなさん、こんにちは。岐阜県郡上市でオーガニックな農家民宿『くらしの宿Cocoro』を営むただっちです。
今をさかのぼること数年前、コロナ真っ盛りの2020年3月頃に始めた「子ども向け 農とくらしのワークショップ」。コロナのせいで学校が休みになっちゃったので、子どもたちも親御さんもさぞ大変だろう、ということで急きょ企画したんです。
ちょっと当時を振り返ってみますと、子どもたちが中心となって農に関わることは、今までの『くらしの宿Cocoro』のワークショップではありませんでした。でも参加してくれたどの子どもたちも、それなりに楽しんで作業をしてくれていました。ま、中にはアッサリ集中力が切れてしまって、どこかへ遊びに行っちゃう子もいましたけど、子どもなんてそれでいいんです。むしろこちらが伝えることを黙々とこなされる方が怖いわ…。
ま、幸か不幸か、マイペースというか独自の世界を持っているいうか。そんな子どもちゃんが多かったので、こちらがそれほど気をもむこともなく自由に農に関わってくれたかな、と思います。
そのワークショップで子どもたちとやった共同作業の1つが、「小さな踏み込み温床」作りでした。今回は3回に分けてその詳細なレポートをしたいと思います。
まずはその導入編として「踏み込み温床とはなんぞや?」についてご説明いたします。
あ、本題に入る前にちょっとお知らせです。
2025年3月16日と3月20日の2日に渡って「小さな踏み込み温床作りワークショップ」を開催します。詳細はこちらから(Instagramに飛びます)。両日とも募集人数に限りがありますので、「踏み込み温床を作ってみたい!」と思われたかたは、ぜひお早めにお申し込みくださいね。
踏み込み温床とは
今ブログを読んでくれているほとんどの方がたぶん見たことも聞いたこともない「踏み込み温床」ですが、その前にそもそも「温床」とは何でしょうか。
タネが発芽するには「酸素、水、温度」が必要です。発芽の三要素、なんて言われます。小学生の時に習ったはずですが、みなさん覚えてますか? ワタクシは農を始めるまで、そんなものスッカリ忘れていましたよ…。
発芽に最適な温度は野菜によって異なります。その中でも特に夏野菜は、発芽に高い温度(地温)を必要とします。温床とはその地温を確保するための仕組みです。読んで字のごとく「温かい床」で、タネをまいた土(培土といいます)を暖めるのですね。
通常、プロの農家は電気を使った温床を使います。こんなのですね。

これと同じものを電気を使わず、微生物の力を借りて発熱させるものが「踏み込み温床」です。これをやや専門的に言うと、こうなります。
踏み込み温床とはワラや落ち葉を微生物が分解するときに発生する熱を利用して野菜苗(特に高温が必要な果菜類)を育苗する技術です。
現在電熱温床が一般的になっているが、簡単に設置でき、温度操作がしやすい反面、電気が必要で内部が乾燥しやすいという問題があります。踏み込み温床は外部エネルギーを必要とせず、適度な湿度が保たれる上に微生物供給と炭酸ガスの交換も行われる苗にとっても優しい育苗でかつ、温床後は再度発酵することで良質の堆肥もできる一石二鳥の技術です。
温床の原理は微生物発酵によるものだが、この菌は落ち葉表面にいる菌を利用するので特に菌の添加は必要ありません。堆肥づくりは急激な温度上昇(60−70℃)が必要で水分60%程度が適正だが、長期的に中温(20-25℃)が必要な温床では、踏み込むことで空気を遮断し、やや嫌気状態でとろ火で燃やす技術です。
ちなみに岐阜県で共に農を営む仲間でもあるブログ主「五段農園」さんの踏み込み温床はこんな感じ。

五段農園さんは堆肥の販売なども行うプロ中のプロ(でも変人中の変人)なので、ワタクシのような小さな農家からすると想像を絶する巨大なサイズの温床を作られています。
が、やることは全く一緒です。
一般的な踏み込み温床の作り方
一般的な踏み込み温床の作り方は、簡単と言えばまぁ簡単です。
最初に枠を作っておいて、そこに落ち葉、青草、ワラ、ヌカ、鶏糞、水などをまいてはガンガン踏み、まいてはガンガン踏み、ミルフィーユのように層を作っていきます。するとそこで微生物が増えたり、微生物が有機物を分解する過程を経て、温床の温度が上昇してきます。
この仕込みの過程で何度も何度も強く踏み込むので「踏み込み温床」と呼ばれるのですね。
一般的な踏み込み温床の問題点(欠点?)
このやり方が伝統的な方法なんですが 、意外と(というか、かなりの高確率で!)失敗します…。以前にワタクシに踏み込み温床を教えてくれた先生は、こともあろうか講義の時に「去年は失敗したけど、今年はどうだろうなぁ」なーんて本音がダダ漏れでしたからね笑
ネットで検索しても「踏み込み温床、温度が上がらない」というような記事がたくさん出てきます。
ふっ、正直言って仕込む前から不安しかないわ…。
そしてネガティブな思考が、まさにネガティブな現実を引き寄せるのですなぁ。イヤな予感は見事に的中し、その年に仕込んだ人生初の踏み込み温床は見事失敗に終わったのでした。
ちなみに踏み込み温床の失敗というのは、たいていこの2つのどちらかです。
- 初めから温床の温度が上がらない
- いったん温度は上がるけど、その温度が持続しない
1は完全な失敗で、2は水分不足による発酵乾燥が原因です。どちらにしても温度が上がらなければ、もう一度最初から仕込み直すしか方法はありません。
で、ワタクシの失敗は1でした。
ま、非の打ち所がない完ぺきな失敗とでも言いましょうかね…。さすがに翌年はくじけて、踏み込み温床作りにトライする気力が湧きませんでした。
そこで登場したのが改良式踏み込み温床!
そんな苦難にあえぐ農民の声を聞いて(かどうかは知りませんが…)開発されたのが、「改良式踏み込み温床」です。開発したのは三重県にある堆肥・育土研究所の代表、橋本力男さんです。

「開発した」ってサラッと書きましたけどね、踏み込み温床って江戸時代から続いていると言われるので、たぶん何百年(最低でも200年くらい)もの歴史がある技術なんですよ。それを1人で根底から引っくり返した男、それが橋本さんです。
ワタクシは2014年に橋本さんに堆肥を学びに行きました。橋本さんは農林水産省が認定する「農業技術の匠」でもあります。堆肥に関する著書も出されていますが、残念なことにすでに絶版になっていて、今ではとんでもない金額が付いていますので、リンクは貼りません。
橋本さんの「改良式踏み込み温床」のスゴいところは、決して失敗しないこと!
踏み込み温床で失敗したことがある人からは「そんな訳あるかーい」と嵐のようなツッコミが入りそうですが…。ワタクシは実際にもう10年近く踏み込み温床を作り続けていますけど、一度も失敗したことがありません。いかに橋本さんの技術が優れているかを、毎年身を以て実感しています。
従来の踏み込み温床と「改良式」の違いを説明します。
従来のものは先ほど書いたように、枠の中に各種材料をまいて水を足しては踏み込み、また材料をまいて水を足しては踏み込み、を繰り返してその後発酵するのを待ちます。
つまり仕込み(=踏み込み)と発酵が一連の作業なんですね。失敗した場合、せっかく踏み込んだものを全部取り出して、もう一度初めから同じ作業を繰り返さなくてはなりません。これがホントにまあ、めちゃくちゃ大変です。
「改良式」ではあらかじめ全ての材料を混ぜて山のように積み上げ、いったんその場で発酵させます。

そして発酵したことをちゃんと目で確認した後(下の写真のようにね)、踏み込んでいくんです。山の状態で発酵が始まらなければ、水を足すなりヌカを足すなりして発酵を促し、温度が上がったことを確認したら踏み込む。
仕込み、発酵、踏み込み、がそれぞれ独立した工程になっています。

踏み込み温床で一番労力が必要な工程は「踏み込み」なので、それが確実に一度で終わる「改良式」は従来のものとは比較にならないくらい楽チンなのです。ま、それでもけっこう体力は使いますけどね笑
さーて、次回は《仕込み編》。果たしてうまく仕込めたのでしょうか。決して失敗しないとか言ってるわりにはちょっと弱気なワタクシですが、乞うご期待です!
《仕込み編》に続きます!
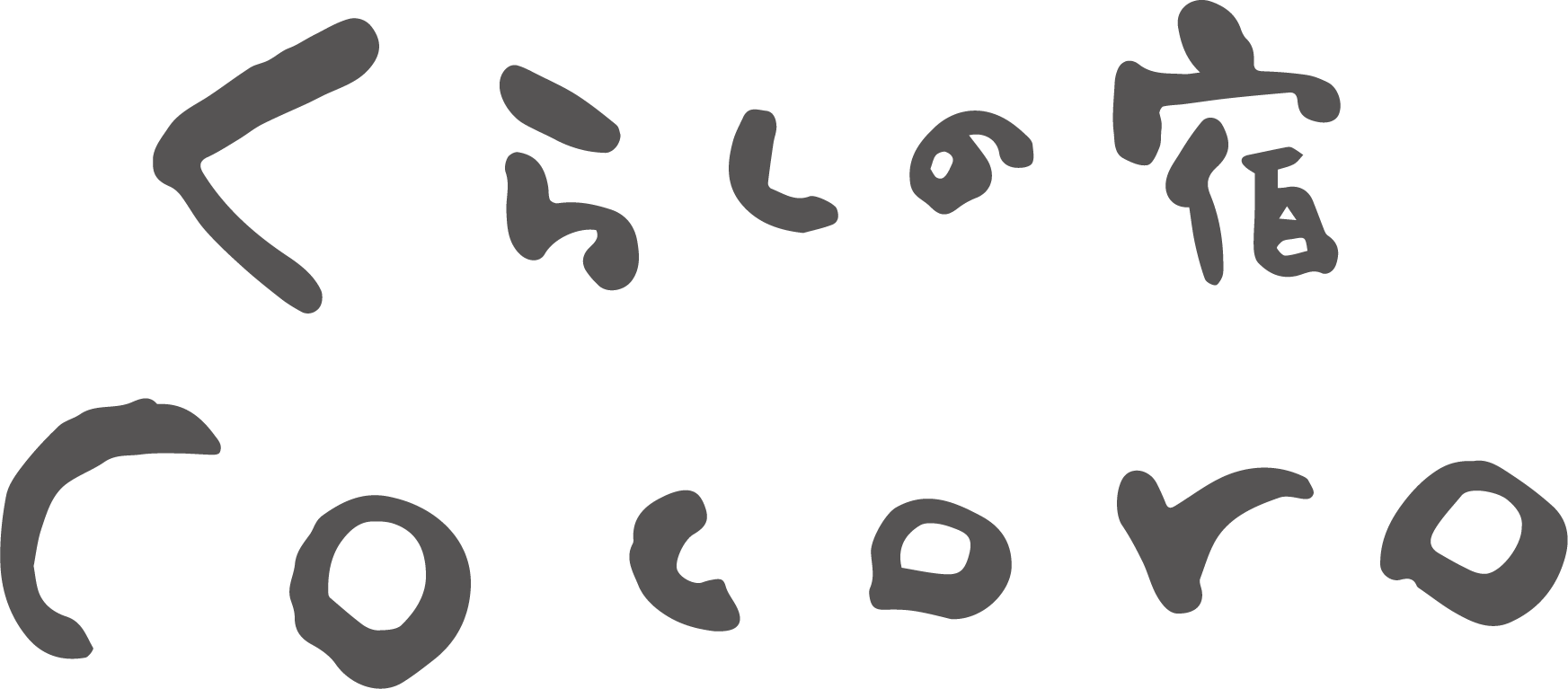

0コメント