みなさん、こんにちは。岐阜県郡上市でオーガニックな農家民宿『くらしの宿Cocoro』を営むただっちです。
今月から始めた「子ども向け 農とくらしのワークショップ」。一部の地域では学校が再開されたりしていますが、まだまだ窮屈な思いをされている方もみえるようです。早くコロナが治まってくれないかな〜。
さて、前回は「踏み込み温床とはなんぞや?」について解説しました。伝統的な踏み込み温床の作り方と、その失敗を根本的に改善した橋本力男さんの「改良式踏み込み温床」についてもご紹介しました。
前回は説明だけで終わってしまったので、今回は写真も交えて「改良式踏み込み温床」の作り方をお伝えしますよ! 以下の文章は全て「改良式踏み込み温床」ですので、お間違えのないようにね。
踏み込み温床の材料とは
踏み込み温床に必要な材料はコレだけです。
- 落ち葉
- ワラ
- モミガラ
- ヌカ
鶏糞や青草などを入れる方法もあるのですが、改良式では使いません。理由は鶏糞が発酵する時にガスを出して、これで野菜の芽がやられちゃったりするからです。青草は表面に付いている菌を利用するためですが、これも腐敗の原因になるので、使いません。
この材料の優れているところは、全てその辺で集められるという点です。ま、伝統的な技術なので当たり前と言えば当たり前なんですけど、永続可能な農という観点からもとっても大事なポイントです!
ここから具体的な作業工程に入ります。
作業その①
落ち葉を集める
まずは落ち葉を集めに山に入ります。子どもたちは山に入るってだけでテンション爆上がり! すぐにどこかへ行ってしまい、もう作業どころではありません(汗) とうぜん写真もありません(涙) ま、状況がいかに大変だったか察してください。
この落ち葉にはいろんな菌が付いています。そして山にはいろんな種類の木がはえています。それぞれの落ち葉に固有の菌が付いているので、この菌たちに頑張って発酵してもらうのですね。
余談ですが時々
「◯◯菌を使おうと思うのですが、どう思われますか?」
なんてご質問をいただくのですが、ほどんどの場面で菌を買う必要はありませんとお答えしています。
だいたい菌ほど不安定なものはないので、よそから持ってきた菌を新たに定着させるよりも、その土地にすでに根付いている菌の方がずっと有効です。しかもタダだしね(笑)
今回は全部で2立米ほど仕込む予定なので、半日かけて一輪車に10杯ほどの落ち葉を集めました。
なーんだ、一輪車に10杯か。楽勝だぜ、と思われた方。甘いっす。一輪車にフワッと10杯なら確かに楽勝なんですが、実はコレ、一輪車に力一杯、ギューギューに押し込んでの10杯です。
計測を始めると、山のように集めた落ち葉がみるみる減っていきます。ホントに足るのかしら、というくらい減ったところで、何とか10杯確保できました!
作業その②
ワラを切る
通常の踏み込み温床ではワラはカットせずに長いまま使いますが、改良式では他の材料との交ざり具合をよくするために、あらかじめ20㎝程度にカットしておきます。
「押し切り」という道具を使います。とっても便利な道具ですが、刃が付いていて危険ですので、充分気を付けて使います。

こいつでザクザクをワラを刻んでいきます。さすがにこれは子どもには触らせられないので、大人が刻みます。
そしてやっぱり子どもたちのテンションがー!
と思いきや、意外と静かにそして慎重に作業を見守ってくれました。
押し切りって見るからに危なそうなシロモノなんですが、そういうのを瞬時に察知するんでしょうかね。う〜む、子どもの直感力、恐るべし…。
ワラは落ち葉と同量です。刻むだけなので大した時間はかかりませんが、お米を育てていない人はこのワラを確保するのが大変です。ホームセンターとかで買うとめちゃくちゃ高いです。踏み込み温床を作りたい人は、前年のうちにお米をやっている農家さんにお願いして、分けてもらうといいかもしれませんね。
今回は一輪車に10杯のワラをザクザクしました。
作業その③
材料を混ぜる
さて、ここへ来てようやく仕込み開始です! いや〜、長い準備でした(笑)
でも農作業って基本的には準備の連続です。タネをまいたり、苗を植えたり、というのはそこまでの準備が終わった、いわば仕上げみたいなもんです。
仕込みはこんな感じで行います。

材料は軽いものから順に重ねていきます。でも今回は軽いものばかりなので、あまり順番は気にする必要はないかな?
最初に重ねる形は平たく、丸く。それぞれの材料で層ができて、まるで大きなホットケーキのような外観になります。子どもたちも
「お料理作ってるみたい」
と、楽しんで作業していました。
で、そこに水をたっぷりかけたら、山にしていきます。

写真ではちょっと大きさが伝わりづらいんですが、直径3メートル、高さ1メートルくらいでしょうか。子どもたちが頑張ってくれたので、まずまずの量が仕込めました!
仕込みはこれにて終了! あとはここにブルーシートをかけ、発酵熱で蒸らします。
個人的にはここが「改良式踏み込み温床」の最大のキモだと思っています。蒸らすことで材料全体に水分と熱が伝わり、ムラのない均一な発酵につながるのですね〜。
というわけで、人事は尽くした。あとは数日後に温度が上がるのを待つのみです。
果たして無事に温度は上がって、ちゃんと仕込めるのでしょうか? ドキドキの《踏み込み編》に乞うご期待です!
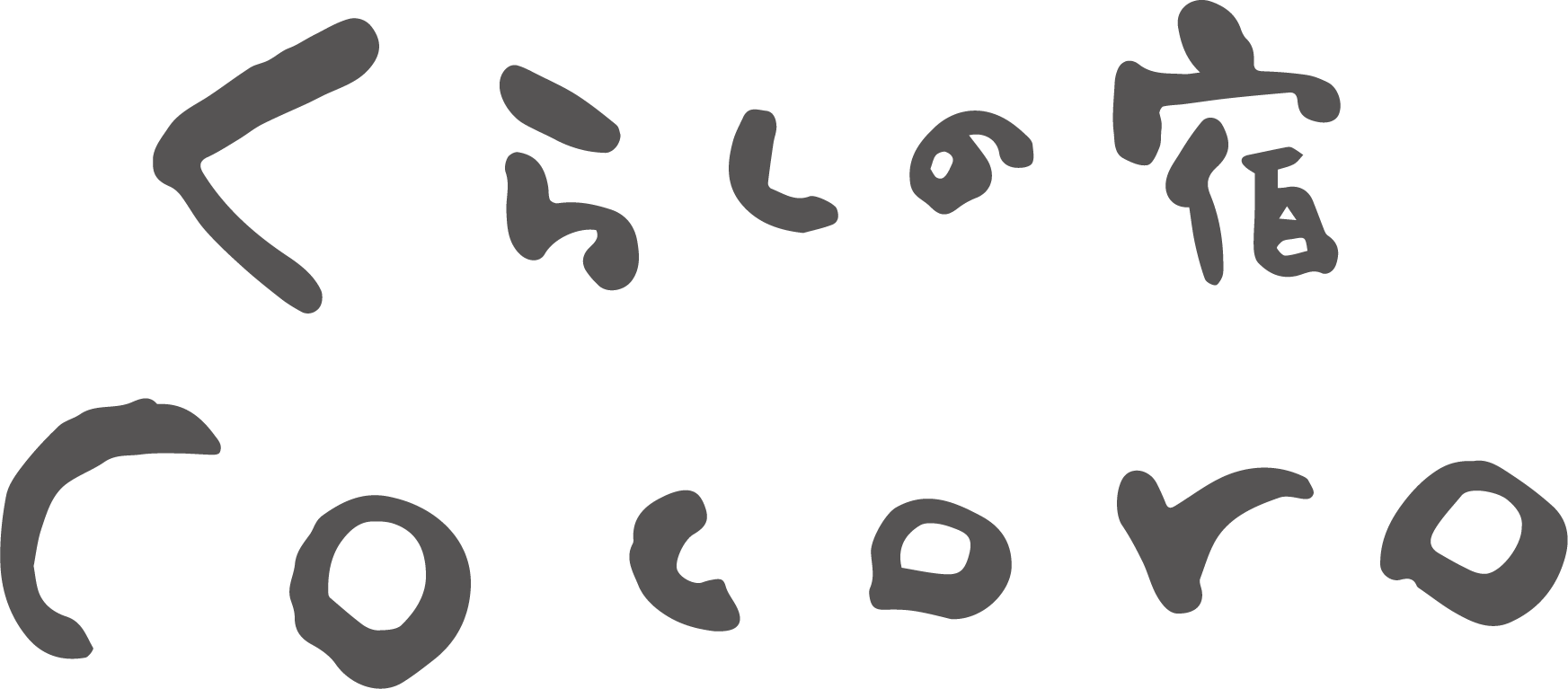

0コメント