みなさん、こんにちは。岐阜県郡上市でオーガニックな農家民宿『くらしの宿Cocoro』を営むただっちです。ここ数日、梅雨の中休みが続いていましたが、今日は梅雨らしくシトシトと雨が降っています。畑にも人にも優しい1日になりました。
今年は田植えイベントを2回開催し、両方とも大勢の方に参加していただくことができました。参加してくれたみなさん、ありがとうございました! みなさんのおかげでとっても充実した田んぼライフを送っています。
が、しかーし! 今年のワタクシは密かに個人的田んぼプロジェクトを進めていたのです。それが何かと言いますと
耕作放棄された田んぼの再生
です!
10年以上耕作放棄されて荒れ放題になってしまった田んぼを、もう一度ちゃんとした田んぼに再生させようというマイプロジェクトです。
ちなみにこの「10年以上耕作放棄されて」ってのはお隣のおじいさんが記憶を頼りにおっしゃっていたのですが、荒れっぷりからするとひょっとしたら放棄期間は15年とか20年とか、そんなくらいかもしれませんね。
ま、10年だろうが20年だろうが、ガチ農家さんにとってはプロジェクトというのも小っ恥ずかしいくらいの内容なんですが…。
て書いてて思ったけど、ガチのプロ農家って田んぼの再生なんて手のかかることあんまりしないよな…。こういうやる前から手間がかかることが分かりきってることに手が出せるのも、小さな農家の特権ですなぁ。
田舎に移住してみたらご近所さんから「今はやってないんだけど」とか言われて、ちょっと荒れた田んぼを貸してもらえる、というケースはよくあります。そんなかたの田んぼスタートアップのお役に立てればと願っています。
ワタクシたちが提唱している「小さな農家」を目指すかたにも、ぜひ読んでもらいたいです。
ちなみに今回再生する予定の田んぼは3〜4畝(300〜400平方メートル)の広さです。「小さな農家」でオススメしている田んぼが5畝(500平方メートル)なので、それよりは少し小さいですね。ま、復旧の作業自体は全く同じなので、参考にしていただければ幸いです。
10年以上放棄されると田んぼはどうなるのか?(5月18日)
こうなります。

「田んぼはどこにあるのですか?」と地主さんに真顔で質問したいくらい、いざぎよい荒れっぷりです。
まず目に付くのはススキ。大人でも抱えきれないくらいの大きな株に育っています。
葛(クズ)も遮るものがないので、のびのびとツルを伸ばし放題。
ツル系では藤(フジ)も侵入しています。
そして田んぼの中に木が生えてますね〜。この田んぼにはウルシの木が何本か生えていました。
あとはひたすら草、草、草。
かつては美しかったであろう石積みの畦はすっかち落ち、田んぼの中には大小の石がゴロゴロしています。
水路もどこにあるのか全く分かりません。
たった10年やそこら放置しただけで、田んぼってこんな風になるんです。そして一度こんな風に荒れてしまうと、なかなか元に戻すのは難しくて、その結果ますます耕作放棄地が増えていきます。昔の人が熱心に田んぼのお世話を続けた気持ちがよーく分かります。
さ〜て、一体どこから手を付けようかな…
なんて考えるヒマもなく、体は勝手に動きます。ここまで荒れはてた田んぼは初めてだけど、過去に何度も耕作放棄地を再生してきた経験と実績がありますからね。もう慣れたものです。
手順その①
草を刈る(5月20日)
ま、順番として当たり前ですわね。
ここは難しいことはもう何も考えずにひたすら草刈りマシーンと化して、草を刈っていきます。刈り払い機という機械があると、とっても便利です。
木が生えているのでそれも頑張って全て切りましょう。木は細ければ刈り払い機で、太かったらノコギリで。とにかくまずは田んぼの地上に出ているものを、全部キレイにする必要があります。
で、切ってみるとアラ不思議。何となく田んぼに見えて、…こないか。

でも草がなくなったことで、どこにあるのか謎だった水路が見えてきましたよ。長い旅路なので、こういう細かい達成感がこの先とっても支えになります。
手順その②
刈った草をどける(5月24日)
お次はその刈った草を、田んぼから出します。これをしないと、このあとの作業が進まないので、大変ですが頑張りましょう。
刈ったその日は草がまだ水分を多く含んでいるので重いです。数日放置してからどけましょう。雨が降るとこれまた重くなるので、お天気と相談して雨が降る前に作業します。
刈った草なんですが、田んぼの外にスペースがあればドサッと山にして積んでおきます。時間はかかりますが、いつか堆肥として使えます。今回は空いている場所がなかったので、数日乾燥させて燃やしました!

ここ数日晴天が続いていたので、いい感じで燃えてくれました。
ここでまず注意してもらいたいのは、野焼きは法律で禁止されていることです。ワタクシたちが住んでいる郡上市でも、もちろん禁止されています。
ごみ(廃棄物)の野焼き(屋外焼却)は禁止されています | 郡上市 Gujo City
ただし、いくつか燃やしてもよいケースが認められていまして、その5にこう書いてありますね。
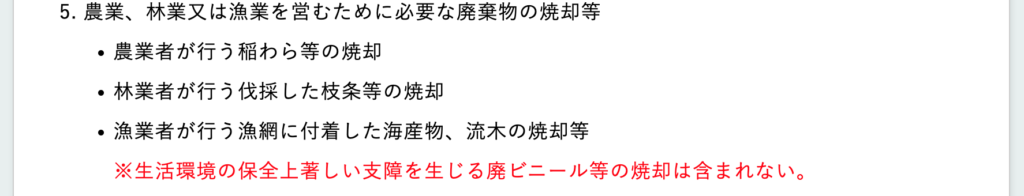
当然と言えば当然です。 ワタクシは農業者の認定を受けていますので、法律的にも条例的にも野焼きをしてもOKなのです。
認定を受けていない人は、お住まいの市町村に相談をしてみましょう。と優等生的に言いたいところですが、その回答もだいたい想像がつきます。たぶん行政は「焼却場に持ち込んでください」と答えます。
今回の田んぼでいえば、軽トラ10杯分くらいの草や木が出ました。それを何度も車に積み込む手間、焼却場へ持っていく時間、そして費用などを考えると、ちょっと現実的ではないですよね。実際には山積みか燃やすか、どちらかの二択になると思います。
山積みはなんの許可もいりませんが、燃やすのであれば農家でないとちょっと難しい。ですので行政に合法的な裏技なんかをもう一度相談してみたり、消防署に相談をして、解決策を一緒に考えてもらってください。もしくは積んでおける場所を探すとか、一緒に燃やしてくれそうな農家を見つけるとか。
野焼きでもう一つ気をつけることは、風向きです。必ず風下から火を付けてください。早く燃えるだろうと風上から付けると、火が風にあおられて草木の表面をすべって燃え広がり、それはそれは大変なことになります(経験あり…)。特に田んぼや畑のような広い面積に火を付けると、上昇気流が起きて火の竜巻が発生したりもします。
正直言って、命の危険を感じるくらいの恐ろしさです…。
なので火をできるだけ小さくして、ジワジワと燃え進んでいく、という感じで燃やしていきましょう。安全な野焼きの方法を具体的に言うと
・刈った草や木は一カ所に集めず、なるべく均等に広げる
・風のない日の、できれば午前中に燃やす(午後は風が吹きやすくなる)
・火を着けるのはまずは一カ所だけ
・消火用の水を必ず用意する
・火を付けたら決してその場を離れない
などが考えられます。
で、燃やしたあとは、ホラこの通り。もうすっかり田んぼに見えて、…こないか。

石をどける(5月26日)
この田んぼ、昔は石積みの畦や土手が巡らされていたようです。それが何度かの大水や獣の侵入などで、すっかり壊されていました。そしてその石が田んぼの中の至る所に散らばっているという、もうとっても残念な状態に…。
このままではトラクターをかけられないので、一つ一つ石を拾っては田んぼの外へ出します。周囲に石積みがあった時代はさぞ美しかったんでしょうけどね〜。石を積む技術はないので今回は諦めましたが、数年後にはチャレンジしているかもしれません。
手順その③
根っこを掘る(5月27日〜6月1日)
田んぼの表面はとりあえずキレイになりました。次はいよいよ未知の世界、地面の中へと突入です!
ススキの根元の株は直径が60センチ以上ありますかね。まずはツルハシやスコップで周囲に穴を掘り、丸太やバールを差し込み、大きな石を支点にしてテコの要領でグイッと、一気に持ち上げます!
はい、一気に持ち上げてっ!
…なのですが、根がビッシリ張っているのでそう簡単には持ち上がってくれません。そりゃそうです。彼らにも生活がかかってますからね。そう簡単にニンゲンにやられる訳にはいかないですよね。
仕方がないので周囲の細かい根を剣先スコップで切ったりして何度もトライします。もうここはひたすら体力と根気の勝負。ノウハウも何もありません。
ススキはススキで大変なのですが、葛はそれ以上にやっかいでした。葛は茎を見たら分かるように、根っこも土の中をツル状に伸びています。それが田んぼの中を縦横無尽に走りまくっているんですよ。
これを手で引き抜きます。スポッとうまく抜けるところはいいのですが、石があったり木の根に絡んでいたりで、その都度作業が中断します。
途中で
「これで葛きりを作ったらたいそう美味いんじゃ?」
という悪魔の誘惑が頭をよぎったのですが、そんな余裕をかます時間も体力もなく。ただひたすらに引っ張っては抜く、引っ張っては抜くを繰り返しました。
そして悪戦苦闘すること数日間。あまりのしんどさに写真は1枚もなし。お手伝いに来てくれた人が腰を痛めたり、アメリカンレーキが壊れたり、はたまたクワが曲がったり、といったトラブルもいくつかありましたが、何とか大きな根っこを取り去ることができたのでした。

そしてコイツの掃除がとっても大切です!(5/24〜随時)
これは手順としては刈った草をどけた後に行うのですが、重要度を考えて一番最後に持ってきました。
さて、草をどけると地面が見えてきます。これだけでずいぶんと田んぼがキレイになったことが実感できると思います。そしてキレイになったからこそ目に付くもの、それは…
ゴミ
です!
その中でも特に多いのが、プラスチックゴミです。畦に入れていたプラスチックのシートとか、草押さえのビニールマルチとか、ビニールひもとか、どこからか飛んできた買い物袋とか。
そんないかにも分解できなさそうな、しかも将来マイクロプラスチックを量産し続けるであろう物質が、後から後から出てきます。それをチマチマと拾っては袋に入れ、拾っては袋に入れ、という非生産的極まりない作業が続きます。

この辺はポイ捨てがーとかモラルがーとか考え出すと作業が進まないので、いっそのこと奉仕作業だと思ってドンドン進めましょう。20リットルのゴミ袋がすぐに一杯になりますよ。そしてたまにデカいゴミが出てくると、まるでお宝を見つけたかのようなステキな気分に、…なるか、そんなもん笑
でもね、今から耕作放棄地を借りて田んぼや畑を始める人にハッキリ言っておきますよ。
最初からキレイな耕作放棄地なんてないから!
キレイな田んぼってのは、誰かがずっとお世話をし続けてきた田んぼなんです。だからキレイ。反対に耕作放棄地ってのは、その作業を止めてしまった田んぼ。だから汚れる。家だって何だって、掃除をサボったら汚れます。だからこれは良い悪いは別にして、当たり前のことなんです。
そして自分たちの手が加わることで、ゴミだらけのこの田んぼが少しでもキレイになるのなら、そりゃーやらない手はないですよ。ゴミの程度にもよるけどさ…。
なんのかんので手作業はこれにていったん終了。後編《機械編》に続きまーす。
[この記事は2020年6月25日に公開した記事を再編集しています。]
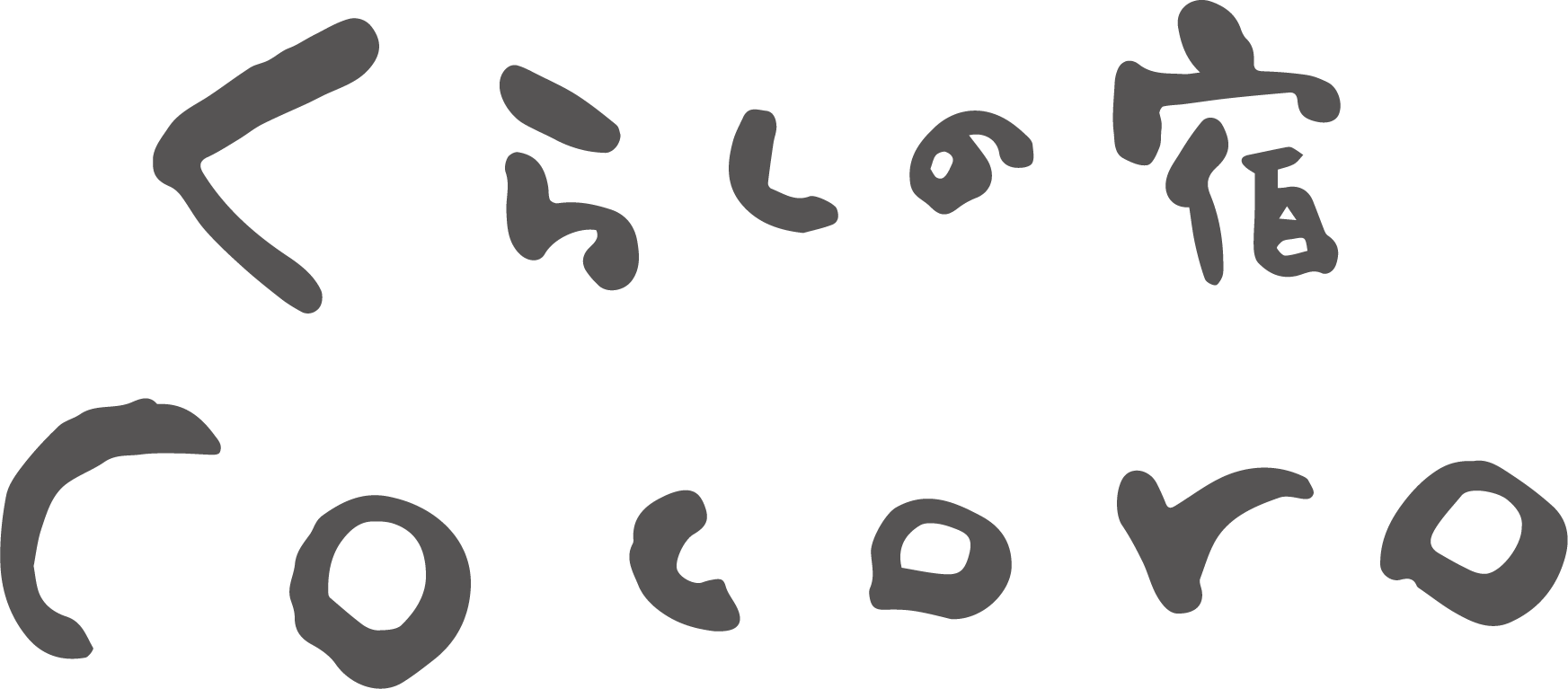

0コメント