みなさん、こんにちは。岐阜県郡上市でオーガニックな農家民宿『くらしの宿Cocoro』を営むただっちです。
今日は梅雨だというのにあまりまとまった雨が降りません。今日は久しぶりの雨。ということで、これまた久しぶりのブログ更新です。この時代、晴耕雨読ならぬ晴耕雨ブログみたいな熟語ができないもんだろうか。なんてアホなことを考えながら書いています。
さてさて、今年も田植えが無事に終わりました!
今年の作付けは田んぼ2枚。1枚は約1.2反、1200平方メートル、そしてもう1枚が8畝(800平方メートル)です。これがそれぞれどれくらいの規模かというと、プロ農家としてはかなり狭い。けど家族でやるにはけっこう大きい。という、ちょっと中途半端な面積です。
『くらしの宿Cocoro』では「小さな田んぼのワークショップ」という講座をかれこれ10年くらい主催しているのですが
今年はそのワークショップに予想を超える人数が集まったので、みんなで全面手植えを行いました!
ひと言で手植えといいますが、実はいろんなやり方があるんですよ! 今日はニッチすぎてそんな話どうでもええわ、いやいや、きっといつかどこかでみなさんのお役に立つ情報をお伝えしたいと思います。
ま、冗談はさておき、もしみなさんが田植えは手でやりたいなぁ、なんて考えていたら、この記事をぜひ参考にしてくださいね。今回は田植えに特化しているので、苗の育て方がとか、自然栽培がとか、耕作放棄地がとか、って話には一切触れませんのでそこんとこ割り切ってヨロシクです!
ではさっそく本題に。手で田植えをするとひと言で言っても、こんなにいろいろとやり方があるんです。
手植えその① ヒモを張る
誰にでもできる、最もオーソドックスかつ初心者向けの方法がこの「ヒモを張る」です。説明の前にまずは写真をどうぞ。

田んぼの端から端までヒモを張り、その真下に植えていく方法です。
1列植え終わったらヒモを30センチずらしてまた植える、を繰り返します。稲と稲は18センチ間隔で植えます。地域によって進みながら植える方法と、バックしながら植える方法があるのですが、ワタクシはバック方式を採用しています。
一番簡単で、失敗も少ないので、初心者にオススメの植え方です。
条間と株間のお話
農業用語では列のことを「条」といいます。条と条の間隔は条間(じょうま)、稲と稲の間隔は株間(かぶま)と言います。ですので先ほどのやり方だと「条間30センチ、株間18センチ」という植え方になります。
条間はどんな場所でも基本的には30センチです。これは日本全国どこへいってもほとんど変わりません。これはなぜかと言うと、法律でそう決まっているからです。
…ウソです。すいません。
これはですね、ごくごく簡単に言ってしまうと「昔からそうだから」です。そんな理由かよ、と思われるでしょうが、実際そうなんだから反論のしようがない笑
ちなみに現代農業では稲を刈り取る時にコンバインという機械を使うのですが、その刃と刃の間隔は30センチです。
昔の道具では田んぼの除草をする田車というものがありますが(こんなのね↓)、これでも除草できる幅もおよそ30センチです。

でも株間は農法によって12〜30センチまで大きく異なります。 一般的には化成肥料や農薬などを使う慣行農法では株間は狭め、無肥料・無農薬の自然農などでは広めになります。理由は長くなるのでここでは割愛します。
自分がどんな農法でやっているのかをちゃんと理解して、それに合わせた株間で田植えをすることがとっても大事です。
時々この理屈を知らずに田植えをしている人がいますが、自分たちの農法を理解した上で田植えをすることが、成功への第一歩ですよー。
手植えその② 筋を引くver.1
こんな道具を使います。名前はなんて言うんだろ。ここ郡上では「筋引き(スジヒキ)」と呼んでいますが、そのまんまですねぇ笑

これを使って田んぼの中に線を引いていきます。これも竹と竹が30センチ間隔ですので、条間は30センチです。
線を真っ直ぐ引くのにコツが要りますが、線さえうまく引ければ、植えるのはとても簡単です。線を引く係は経験者にお任せしましょうね。

この時は線に沿って前進しながら植えていきます。バックで植えるとせっかく引いた線が消えてしまうので、注意しましょう。
手植えその③ 筋を引くver.2
こんな道具を使って筋(というか印)を付けることもできます。この道具の名前は分からないんだよなぁ。ご存じのかたがいらっしゃったら、ぜひ教えて下さい。

木でできた枠をゴロゴロと転がして印をつけます。
枠を構成する四角形は30センチ四方で、このクロスしたところに稲を植えていきます。なので条間も株間も30センチになります。この方法も誰にでも簡単に田植えができるので、農業体験などではよく使われていますね。
でもですね…
枠を真っ直ぐ転がすのが超難しいのですよ。ワタクシは過去に一度だけトライしましたが、見事に撃沈しました。どうしても曲がってしまうんだよなー。あと枠が大きくて重いので、道具を持ち運びするのも、保存する場所にも苦労しました。便利な道具だとは思うのですが、個人的にはちょっと苦手な方法です。
手植えその④ 究極はコレだ!
これもヒモを張る方法なんですけど、上級者向けです。理由は後で説明しますが、初心者の方は絶対に手を出さない方がいいです。

右端の二本のヒモが見えますか?
ヒモを複数本張って、その真下とその間に植えていきます。このやり方だと1人で一度に8条くらい植えることができます。少人数でスピード勝負! という時はこのやり方が向いています。
ヒモの下は真っ直ぐに植えれますが、ヒモとヒモの間がかなり難しいです。慣れない人がやると、ガタガタになりますので、初心者は絶対に手を出しちゃダメです。後々の管理がむちゃくちゃ大変になります。
でもこの写真ではラインが真っ直ぐにビシッと出ていますね〜。さすがワタクシだな(自分で言うな)。
どうですか、みなさん。田植えしたくてウズウズしてきたでしょ。

来年も再来年も「小さな田んぼのワークショップ」は開催します! 気になったかた、田んぼをやりたいかた、ぜひ郡上にお越しください。
宿へのご宿泊もお待ちしていまーす。田んぼトークしましょうね〜♪
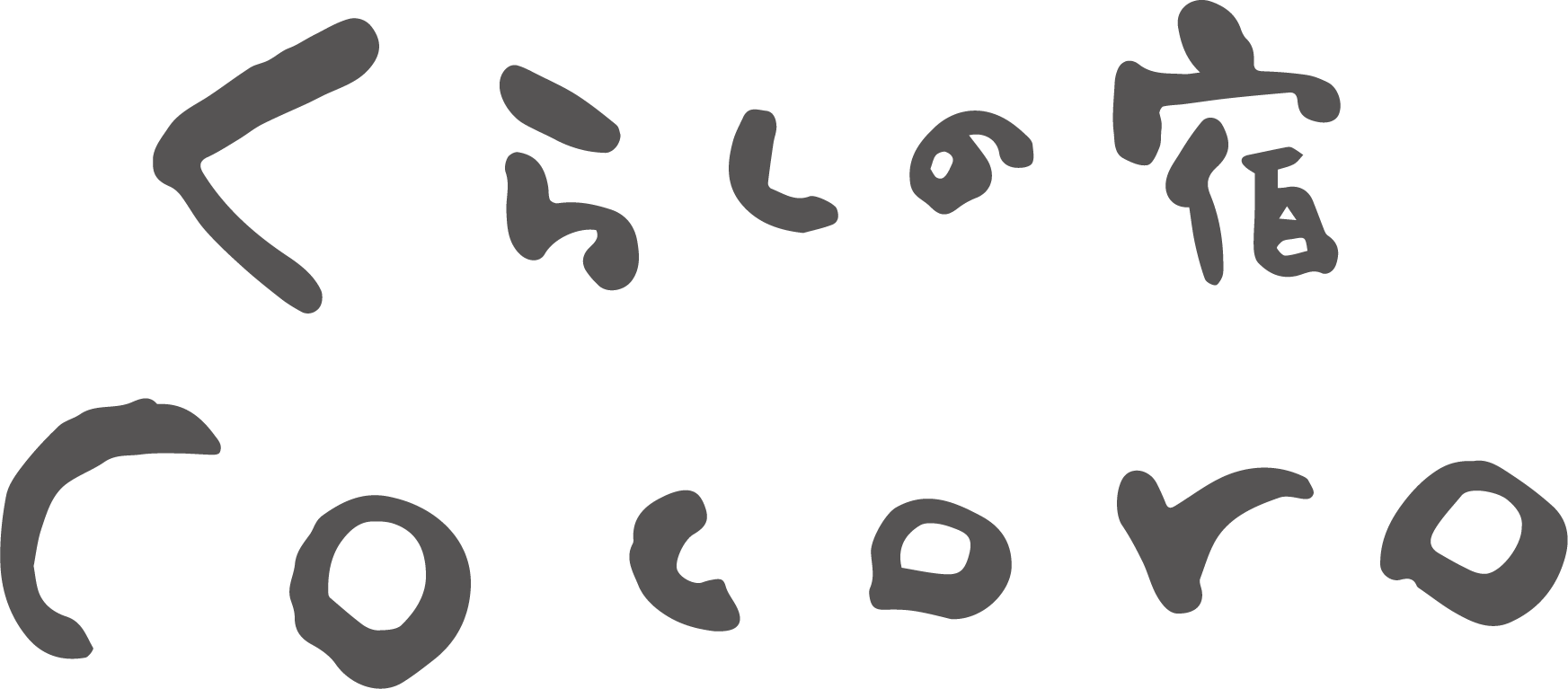

0コメント