※この記事は2019年11月に公開したものを、文章の加筆修正・写真の変更などを行い、2023年2月に再度公開したリライト記事になります。
みなさん、こんにちは。岐阜県郡上市でオーガニックな農家民宿『くらしの宿Cocoro』を営むただっちです。
ここ数日、晴れては時雨、の繰り返しです。岐阜の山間部ってどこもこんな感じなのかなぁ。畑に行こうと思うと雨が降ってきます。雨だしデスクワークだ、と思うと晴れます。よし、じゃあ布団を干そうと思うと、また降ってきます。ん〜、どっちやねん。晴れるか降るか、どっちかにして欲しいぞ!
先日、小さな田んぼの仲間たちと収穫祭を開くことができました。今年もお米が取れて良かったね〜、来年も楽しんで田んぼがんばろうね〜、ってな感じで毎年開いている、感謝の会&お疲れさま会です。

『くらしの宿Cocoro』では愛農かまどで今年の新米を炊き、畑で取れた野菜たっぷりのお味噌汁を作り、みなさんからはご自慢のお料理を持ち寄ってもらいました。愉快な仲間と美味しい料理に囲まれて、とてもにぎやかな収穫祭になりました。あ〜、楽しかった。みんな、ありがとね。

今回はワタクシたちが今までどんな経緯で田んぼに関わってきたのか。そしてあちこちで小さな農を営んでいる仲間たちについて書いてみようと思います。
小さな農家を増やす
これは『くらしの宿Cocoro』が長年、しかも細々と取り組んでいる活動です。ワタクシたちが宿をやったり、農の講座を開いている目的とも言えます。「小さな農家」というのは、家族みんなで自分たちが食べるお米や野菜を育てようよという、要は食べ物を自給する暮らしの在り方ですね。
スーパーで食べ物を買うのもいいけど、自分たちで育てた野菜やお米はやっぱり格別だよね〜! オーガニックの野菜はちょっと高いけど、自分で育てればスーパーで野菜を買うより安いしね♪ ってな感じです。そしてここ数年は©やらウクライナ問題やらで、自給に関する注目がますます高まりつつあると感じています。
そんな小さな農家仲間を増やすために、ワタクシたちは畑や田んぼの技術をワークショップ形式(座学と実技)でお伝えしています。意外にも畑より田んぼの方が簡単で、1年間(約10回)のワークショップを受けることで、翌年からは自分で田んぼができる実力がつきます。中にはツワモノがいて、うちでワークショップを受けながら、同時並行に自分で田んぼをやっちゃう人もいます(結果的にはそれが一番学びになります)。
ワタクシたちは畑や田んぼの楽しさを知っているので、人に会うたびに「田んぼやれー、畑やれー」と呪文のように唱えています(ウソですけど)。
人間、同じことをしつこく言い続けていると現実がそっちに寄ってくるみたいで、ありがたいことに小さな農家が少しずつ増えてきました。詳しくはコチラから。
そんな気の置けない仲間たちとの収穫祭。盛り上がらないわけがありません。
でもみんなの話題は田んぼのことばかり。田んぼオタクかよ(笑)
今年の失敗やら成功、来年への豊富、こんなことをしてみたい、あんなことをしてみたい。あー、話を聞いているだけで来年への期待が膨らみます。いやー、今年も楽しかった。仲間たちとこういった時間や話題を共有できるのって、本当に幸せです。
田んぼを始めたきっかけ
ワタクシたちが田んぼのワークショップを始めて、今年(2023年)でちょうど10年になります。参加してくれたのは延べで100組を越え、人数にすると400〜500人くらいかなぁ。で、その中で自分で田んぼを始めちゃった人が12〜13組くらい。7〜8組に付き1組ほどの割合になりますね。毎年、という訳ではないけど、2年に1組以上は田んぼを始めちゃった人がいる計算になります。
最近では郡上に移住してきた人と話していると、必ずと言っていいほど「田んぼやりたいんですよね」という話になります。ま、そんな人たちだからこそ移住してきたという面もあるのですが、ワタクシ個人的にはいい流れだなぁと感じています。
ところでみなさん、田んぼって素人にはできないような気がしませんか?
「家庭菜園」はよくあるけど、「家庭田んぼ」ってあまり聞いたことないですよね。実はワタクシたちも農家になった最初の年(2012年)は、畑しかやっていませんでした。田んぼは自分たちにはできないもんだと、勝手に思い込んでいたのです。
でもね、相方が言うわけですよ。
「せっかくならお米も育てたいよね」
うん、気持ちは分かる。けどやり方が全く分からん…。
そんなある日、名古屋で田んぼの有機栽培の講座が開かれるという情報が! よし、コレだー! と思い、さっそく岐阜から話を聞きに行きました。
オーガニックファーマーズ名古屋(オアシス21オーガニックファーマーズ朝市村)さんが主催する講座でした。時間は1時間半くらいだったかな。40〜50人くらいの有機農家を目指す人や、すでに就農している人たち人が話を聞きに来ていました。
講師は岐阜県白川町(合掌造りの白川村とは別です)のベテラン農家、中島克己さんという方でした。当時60代後半だったでしょうか。
中島さんは熱く語ってくれました。
「田んぼに農薬を使わんようになるとな、いろんな虫が来るんや。これがかわいくてな♡」
「今までは農薬を使っとった。でも薬を使わんようになると、いろんな虫がやって来るんや♡」
「虫はかわいいぞ♡ 殺したらアカンぞ」
わざわざ名古屋まで田んぼの話を聞きに行ったのに、90分のうち70分くらいは
「虫はかわいい♡」
という内容でした…。技術的な話は10分くらいあったのかな、いや、なかった気がするな…。そんな中島さんの話を聞いて、
これなら絶対ワタクシにもやれるハズだ!!
と確信したのです!(笑) 中島さん、スゲーぜ!
翌年から田んぼを始める
そこで翌年2013年から、さっそく田んぼを始めました。当時ワタクシたちが住んでいたところは耕作放棄地が多くて(というか耕作放棄地の方が多いくらい…)、田んぼはすぐに見つかりました。
でも中島さんのお話しだけではさすがに田んぼはできません(技術論が全くなかったしな…)。そこで中島さんがお住まいの白川町にあるNPO「ゆうきハートネット」が主催する有機稲作の講座に通い、そこで勉強をしながら同時並行で田んぼをすることにしました。
結果的にこれがとても良かったのです。
何が良かったかって、学んだことをすぐに実践すると、だいたいどこかで失敗するんですね。でもつい先週とかに学んだばかりなので、講師のアドバイスを思い出せるんです。講義中は分からなかったことも、自分でやってみると理解できます。
そして結果的には、ワタクシたちのような素人でも1年目からちゃんと田んぼができるんだ、と実感できたことも良かったです。今まで田んぼはプロの農家(ってワタクシたちも一応プロですが…)がやるもので、素人には難しいと思っていたのに、それが大きな勘違いだと分かりました。
で、そんな手探り状態で田んぼに挑戦した1年目。結果はなんと大豊作でした! えー、こんなに取れちゃっていいの? とビックリしたのを今でも覚えています。

そして周りの人たちももちろんビックリでした。だってほぼ素人が無肥料・無農薬で田んぼをやって、しかも初年度から成功するなんて、自分たちでも思ってなかったからね〜。
ワタクシたちがどんな風にお米を育てているのかを知りたいかたはコチラを読んでね!
ぶっちゃけ言いますと、実は田んぼってね、技術的にはそんなに難しくないんですよ(あーあ、言っちゃったよ…)。手間も労力ももちろんかかりますが、田んぼに必要な技術を習得することはそんなに難しくはない。
田んぼをやる上で一番高いハードルは、地域との関わり方や水なのです。
「水利権」と言います。読んで字のごとく、水を利用する権利です。地域によっては「よそ者には水は使わせん」というような所も、実際にまだあります。なので田んぼをやりたい方は、水を使わせてもらえるかどうかをしっかりと確認する必要があります。
それがクリアーになれば、誰にでも田んぼはできます。
だってお米って主食ですよ? ご先祖さまは弥生時代からずーっと稲作をやってきたんですよ? そんな大切なものがワタクシたちにできないハズがないんです。
その翌年からワークショップを主催する
そして1年目のこの成功で調子に乗ったワタクシは、翌年から田んぼのワークショップを始めたのでした!
ってのは半分冗談、半分本気です。
ワタクシたちは基本的な技術だけで、初年度にそこそこの成功を収めることができました。それが単なるビギナーズラックではなく、技術に裏打ちされた結果だということも実感できました。
ということはですよ、ワタクシたちがその技術をいろんな人に伝えたら、みんなが田んぼができるんじゃないの?
じゃあ家庭田んぼできるじゃん! と思ったのです。
そこで独自のプログラムを作り、参加者を募って田んぼのワークショップを始めたのですね。ちなみに現在は「小さな田んぼのワークショップ」と言っていますが、2013年当時は単に「田んぼワークショップ」と呼んでいました。
ワタクシたちが農家になって初めて主催する、記念となるワークショップでした! 最初は参加者さんが集まるかどうか不安でしたが、なんとこの年は募集を開始してすぐに満員御礼! 申し訳ないことに、お断りする人まで出てしまいました。
ふふふ。みんな、田んぼやりたかったんだね。
そしてHさんがやってきた
そんな田んぼのワークショップを始めて数年経った頃のことです。
いつものように参加者のみなさんに作業の手順やその意味を説明していました。ワタクシも講師として経験を重ね、今や説明も進行も慣れたもんです。
…って、すいません。ウソつきました。学ばない男、ワタクシ。いつもバタバタと失敗続きでゴメンなさい(汗)

まだ肌寒い3月のことでした。その年にまく種モミを選別する、塩水選という作業をしていた時のことです。参加者さんが輪になってワイワイと作業しているのに、その輪から外れてチョー不機嫌な顔をしている1人の男性がいたのです。
最初は何か個人的な理由で怒っているのかと思ったのですが、どうやら違います。言うなれば不審者を見るような目で、ワタクシや他の参加者さんを見ています。
「お前たち、何おかしなことやってんだよ?」的なオーラをバンバン発しながら。
このワークショップは、決して安くはない参加費を払って参加してもらっています。今まで積極的な方はたくさんみえましたが、そんな不可思議な雰囲気をかもしだす参加者さんは、1人もいませんでした。
それがHさんでした。
ええっと、彼に一体何があったのかしら…?
後半に続きます。
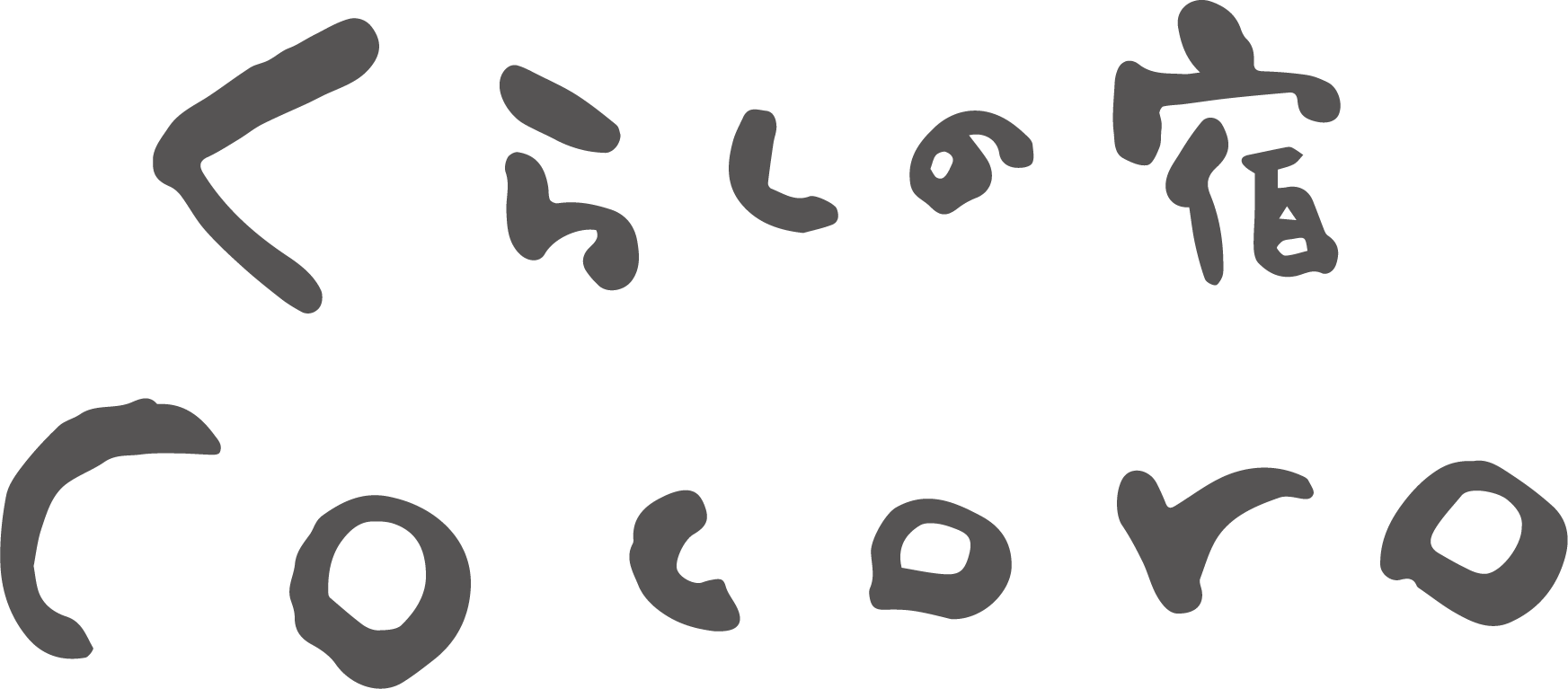

0コメント