みなさん、こんにちは。岐阜県郡上市にあるオーガニックな農家民宿『くらしの宿Cocoro』を営むただっちです。
毎年大忙しのお盆が今年も無事に終わり、ついでに酷暑も終わり、ようやく秋の気配が漂ってきました。この夏も『くらしの宿Cocoro』にお越しいただいたみなさん、本当にありがとうございました! ステキな時間をお過ごしいただけたなら幸いです。
さて、そんな激動の季節を乗り越えてちょっと一息つきたい今日この頃ですが、迫り来る冬を前に張り切っていきますよー。
田んぼをやりたいみなさん、長らくお待たせしました! 今回は3年ぶりの開催となります
「田んぼと暮らす。休耕田再生ワークショップ」
のお知らせです。
前回の開催が2022年だったので、もう3年前になります。ちょうどコロナ騒動が盛り上がっていた頃ですね。そんな状況下でも満員御礼だったので、人がそういう時に農や暮らしに期待するものって大きいんだなぁと思った覚えがあります。
どうして3年ぶりの開催になったのか?
それはですね、友人から「うちの使っていない田んぼを復活させたいんだけど、やり方が分からないので教えて欲しい」というリクエストがたまたまあったからです。
いくらワタクシが「よっしゃー、毎年田んぼの復活をするぜ!」と意気込んでみたところで、耕作放棄された休耕田が見つからなければできません。
そして諸事情で田んぼをやめる人は毎年たくさんみえますが、耕作放棄されて荒れ果ててしまった休耕田を復活させたい人はそんなにいません。さらにはその田んぼを学びの場として貸してくれる人も、あまりいらっしゃらないのが現状です。
ありがたいことに今回は良い機会に恵まれましたので、こうして3年ぶりにワークショップが開催できることになった訳です!
このワークショップがどのような内容なのかをざっくり3行でまとめますと
「休耕田を元に戻すにはどうしたらいいのか?」
「農家ではない人が田んぼを始めるにはどうしたらいいのか?」
「そしてその田んぼで稲作をするにはどのような技術が必要なのか?」
をお伝えするワークショップです。内容は座学とワークショップ(実技)の2本立てです。
座学で具体的に田んぼの始め方、技術、必要な道具や機械などをお伝えして、ワークショップではみんなと一緒に頭と体を動かして、翌年からみなさんが田んぼを始めるお手伝いができればと思っています!

田んぼを始めるのって難しい?
ワタクシは農家として今まで数々の相談を受けてきたのですが、農家じゃないしもちろん農地も持ってないけど田んぼを始めたいんです! とおっしゃるかたは想像以上に多いです。特に田舎暮らしに憧れて移住してきた人なんて、全員田んぼやりたいんじゃないの? くらいに感じる時があります(やや妄想が暴走か?)。
でも田んぼを始めるのって、何となくハードルが高い気がしませんか? 周りを見ても家庭菜園はよくありますけど、家庭田んぼってあんまり聞かないですもんね。有機農家仲間でもやっているのは畑だけ、という人が何人かいます。
では田んぼのどんなところが大変なんでしょうか? 田んぼを始めるに当たって乗り越えるべきポイントは多々あるんですが、すごく分かりやすい点を1つ挙げてみましょう。
それは田んぼには特別な機械がいろいろと必要ということです。
畑ですと極端な話、鍬(クワ)と鎌(カマ)さえあればあとは人力で何とかなります。でも田んぼだとそういう訳にはいきません。現在一般的な田んぼで使用されている機械をざっと挙げてみると
・トラクター
・トラクターに付けるアタッチメント各種(ロータリーやドライブハロー、畦塗り器など)
・田植え機
・コンバイン
どれもこれも大型でしかも高価な機械なので購入には一大決心が必要ですが、保管する格納庫や維持したりする費用なども、これまた大変です。

さらにはお米を刈り取ってからも
・乾燥機
・籾すり機
・精米機
といった機械が必要になってきます。
それ以外の細かいところでも、稲の苗を育てるための「育苗箱」、脱穀したお米を入れる「コンバイン袋」、お米の「保存庫」なんてものも必要ですね。
この「機械の多さ=初期投資の大きさ」が、田んぼを始める上で大きなネックになっていることは間違いありません。
ただしこれはそこそこ大きな田んぼをやる場合のお話なんです。ワタクシがみなさんにお伝えしている自給向けの「小さな田んぼ」では、実はかなり様子が異なります。
これまた分かりやすい一例を挙げますと田植え。機械ではなく手で田植えをすれば、当然ですが田植え機は要りません。手植えはこんな感じで行います。
田んぼの作業を全て人力で、というのは実際にはけっこう難易度が高いですが(世の中にはそんなツワモノもいらっしゃいますが…)、一部の作業を手でやる、もしくは自然に任せることで、機械を大幅に減らすことが可能なのです。
また機械とひと言で言っても、大きな田んぼに向いた物と、小さな田んぼ向けの物があります。もっというと機械ではなく、人力で動かす道具なんて選択肢もあります。
どういう機械や道具を選べばいいのかを実際の作業内容に沿って、できるだけしっかりじっくりお伝えすること。そして「小さな田んぼ」を始めるイメージを具体的に掴んでもらうことが、この講座の目的です。
場所
講座の開かれる場所は郡上市大和町にある「ねこのま」さん。来年の春頃に開業を予定されている猫専用ペットホテルです。
日程
2025年11月22日(土)~23日(日)にかけ、2日間に渡って行います。
せっかくの機会なので遠方の方にもにお越しいただけると嬉しいです。
幸い郡上には宿泊施設がいっぱいありますし、「ねこのま」さんの母体は郡上八幡にあるゲストハウス「まちやど」や「タテマチノイエ」さんですので、そちらへのご宿泊もできます(宿泊のご予約は各自でお願いします)。
今回は『くらしの宿Cocoro』にはご宿泊はできません。ワークショップの講師を務めながら宿のおっさんもこなす、というのはキャラの切り替えが大変だからです笑
初日の座学終了後には情報交換会という名の宴会も予定されているとか⁉ う〜ん、こりゃ初日からヤベーことになりそうな予感がヒシヒシとしますねぇ。
定員と応募締め切り
定員は最小3名、最大10名です。3名に満たない場合は開催ができませんので、みなさん奮ってご参加ください!
応募の締め切りは10月31日(金)です。募集人数を上回った場合は、志望動機などを勘案し、11月5日(水)までにご参加になれるかどうかをご連絡いたします。
参加費
参加費はお一人さま27,000円です(LINEによる1年間のサポート代・テキスト代・傷害保険・初日の夕食と2日目の昼食代を含む)。
※宿泊費は含まれませんのでご注意ください。
内容
初日:座学
初日は座学です。13時より受付を開始し、13時半スタート。講義が終わるのは17時の予定です。内容は大きく2つに分けられます。
前半:休耕田の直し方と小さな田んぼの始め方
休耕田の問題点、田んぼを始める際の手順、地域とのお付き合いの仕方、水利権の説明、注意点、初心者がやってしまいがちなミスなどなど。
前半ではワタクシの経験(華麗なる失敗とも言いますが…)に基づいて、初心者が押さえておくべきいわば「田んぼの作法」についてお伝えします。実は田んぼはこの作法がすごく大事で、ここがうまくできないことで地主さんとの関係性がこじれてしまい翌年から田んぼを貸してもらえなくなった、なんて話も時々耳にします。
村社会独特の、と言ってしまうとやや大げさかもしれませんが、農の教科書には載っていないリアルを感じてもらえると思います。
後半:有機稲作の技術講習
後半では無肥料・無農薬の有機稲作で稲を育てるためのさまざまな技術を、写真などを交えて具体的にお伝えいたします。先ほど書きました「どういう機械や道具を選べばいいのか」についても、写真を交えつつお伝えします。
『くらしの宿Cocoro』オリジナル田んぼのカレンダー(栽培歴)もお渡しいたしますので、来年から田んぼを始めたいかたはぜひ参考にしてください。これがね、また大変良くできているのですよ、って自分で言うな。

2日目:ワークショップ
2日目はワークショップです。「ねこのま」さんにある長年耕作放棄された田んぼを自分たちの手で直し、来年から田んぼができる状態にまで完全復活させる予定です。広さは約6畝(600平方メートル)ほど。自給向けの小さな田んぼとしてはまさに理想的な広さです。

時間は朝9時から16時くらいまでを予定しています(参加人数によっては早めに終わることもあります)。1日ガッツリ作業する、というよりはみんなでお話をしながら、協力をしながら、いろいろ考えながら、気づいたらもう終わりなんだね、みたいな頭と体を使うワークショップになるといいなと思っています。
なぜ2日目にこのワークショップを組み込んだかを簡単に説明しますと、郡上のような山間部で農家ではない個人が貸してもらえる田んぼって、まず間違いなく長年耕作放棄された小さな田んぼなんですよ。
面積的には1000平方メートル以下、農業用語で言うと1反以下のものがほとんどです。なぜかというと、大きな田んぼはすでに大規模な農家さんが借りているからです。どうしても残り物(と言ったら失礼ですがね…)が回ってくるんです。
しかしその残り物にこそ福がある! とたくましく考えるのが我々「小さな農家」です。どうしてかというと…、というお話しは当日のお楽しみ。ここであんまり書きすぎると当日話すことがなくなっちゃうからね。
で、大体の場合その耕作放棄された田んぼを再生(正しくは再開墾とか言うのかな?)するところから作業が始まる訳です。そしてこの再生のやり方1つで、後々田んぼの使い勝手がずいぶんと変わってくるんですね!
試しに「田んぼ 開墾」とか「田んぼ 復活」とかのワードで検索してみてください。もう出るわ出るわ。世の人がいかに休耕田の復活に心血を注いでいるかがよく分かると思います。
ちなみにワタクシも今を去ること数年前の2020年に、休耕田の再生に取り組みました。どんな作業だったのかはこちらの記事にまとめてあります。ワークショップに参加される方は必読です!
今回のワークショップでは、これとほとんど同じ作業をみなさんにやっていただきます。ワタクシの田んぼとの大きな違いは、機械を使わずに全て手作業でやるという点です。
今回なぜあえて機械を使わないのか。いろいろと理由はあるのですが、これも詳しくはワークショップでお話しをいたします。
「田んぼと暮らす。休耕田再生ワークショップ」のお問い合わせやお申し込み先はこちらです(募集は締め切りました)。
それではみなさん、11月に「ねこのま」さんで会いましょう!
田んぼ楽しいよ〜♪
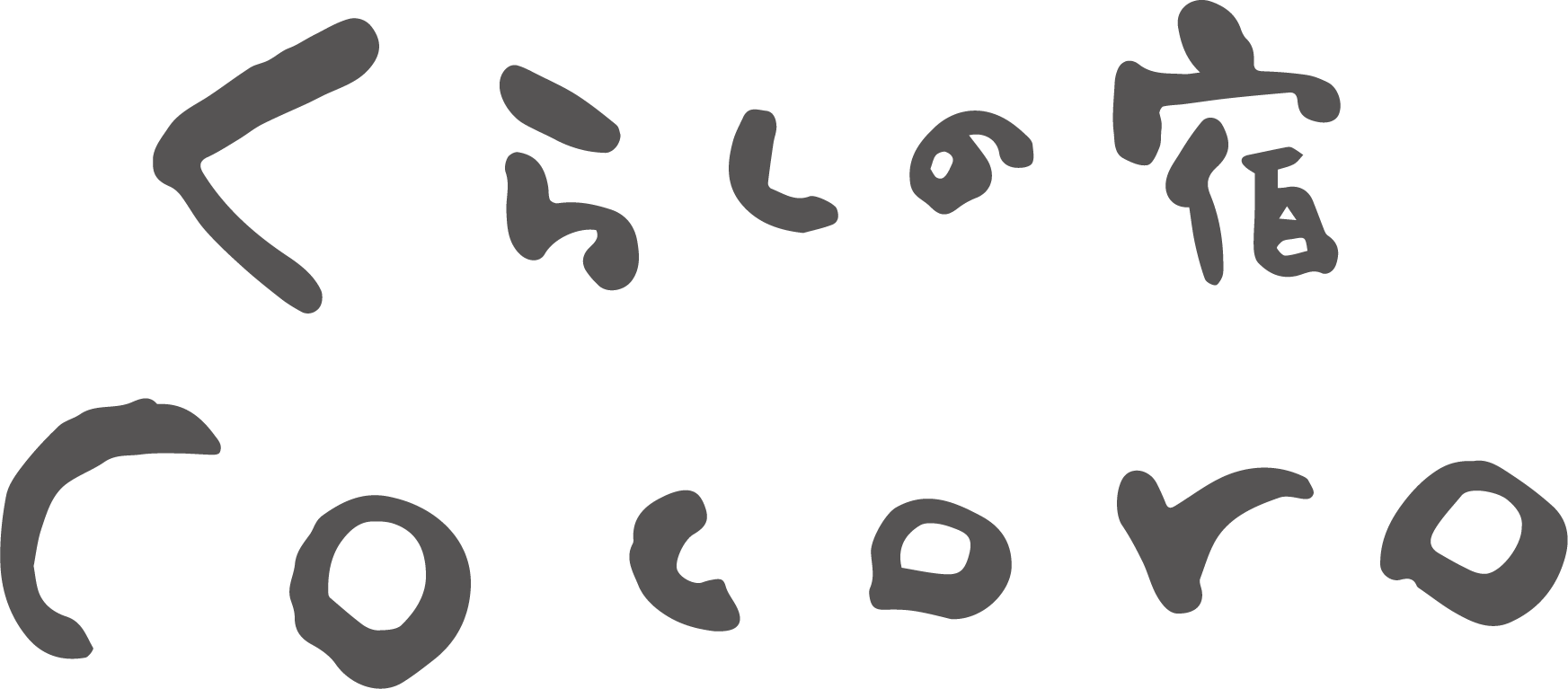

0コメント